危険物施設とは?どんな種類があるのか解説

「危険物」と聞くと、名前の通り、人体に何らかの危険がある怖いもの、というイメージがあるのではないでしょうか。また、危険物施設といえば、どこか人里離れた見えない場所にあるように感じられるかもしれません。しかし、実は危険物と呼ばれるものの中には、たとえばガソリンのように私たちの生活に欠かせない物質もたくさんあり、街中など身近なところに危険物施設は存在しています。
ここでは、そうした危険物施設の種類について説明します。
目次
危険物施設とは何か?
「危険物」には、大きく分けて「消防法上の危険物」と「毒物及び劇物取締法上の危険物」の2種類に分けられています。
消防法上の危険物

「消防法上の危険物」とは、一般的に、火災発生の危険性が大きいもの、火災拡大の危険性が大きいもの、消化の困難性が高いもの、つまり火災につながる危険性が高いものが主な対象です。
消防法上の危険物は、第1類~6類まで分類されており、それぞれの特徴は以下の通りです。
第1類「酸化性固体」:塩素酸ナトリウム、硝酸カリウムなど、そのもの自体は燃焼しないが、他の物資を強く酸化する性質があり、可燃物を激しく燃焼させる危険性のある個体。
第2類「可燃性固体」:硫黄、鉄粉、固形アルコールなど、40°C未満の比較的低温でも引火しやすく、燃焼も早く、消火するのも困難、つまり非常に燃えやすい個体。
第3類「自然発火性物質及び禁水性物質」:カリウム、ナトリウム、など、空気中で自然発火しやすい、または水と接触することで発火する個体や液体。
第4類「引火性液体」:ガソリン、灯油、軽油、重油など、引火性を有する液体。引火性液体は、さらに、引火点の違いなどにより、第1石油類(ガソリン等)、第2石油類(灯油、軽油等)、第3石油類(重油等)などと細かく分類される。
第5類「自己反応性物質」:ニトログリセリン、トリニトルトルエンなど、固体、または液体で、比較的低い温度で多量の熱を発生し、それ自体が酸素供給体でもあるので、空気に触れずとも燃焼し、爆発的に反応が進行する。
第6類「酸化性液体」:過酸化水素、硝酸など、それ自体は単独で燃焼することがない液体ながら、他の可燃物を酸化させ燃焼を促進させる性質があるもの。
危険物施設とは、こうした「消防法上の危険物」について、指定数量以上を製造・貯蔵・取り扱いなどする建物のことを指しています。
毒物及び劇物取締法上の危険物
一方、「毒物及び劇物取締法上の危険物」は、吸引や接触によって、人や動物の生理的機能に害を与える化学物資が主な対象です。
危険物施設に関する法律やガイドライン
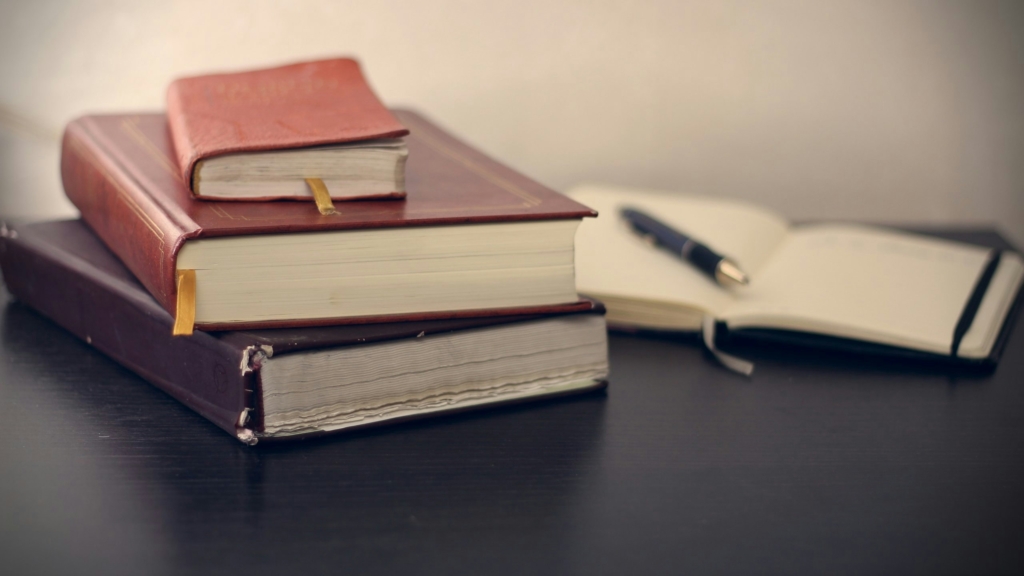
危険物施設には、火災の発生予防、延焼予防、被害を最小限に抑えるための、さまざまな構造上や設備上の基準が設けられています。また、危険物施設は、震災時におけるライフラインの役割を果たす重要な施設でもあるため、東日本大震災を教訓に、総務省からは震災等に対する、事前対策、災害対応、使用再開に向けたガイドラインが策定されています。
次項に挙げる危険物施設の種類によって、法律は細かく規定され、ガイドラインは策定されています。
危険物施設の種類
危険物施設は、扱う危険物の用途に応じて、「危険物製造所」「危険物貯蔵所」「危険物取扱所」の3つに分類されます。その中でさらに種類分けがされ、それぞれに構造や設備上の基準が設けられています。
危険物製造所
危険物を製造する目的のために作られた施設です。種類は1つだけですが、構造、設備、配管において、細かな基準が設けられています。
構造については、壁や屋根などには、延焼を起こしにくい不燃材料を使用、また、屋根は万が一の爆発の際、空気が抜けやすくするため、金属板などの軽量な素材でなければならないなどの規定があります。
設備においては、避雷針や排気口の設置、必要な明るさを確保するための採光窓の設置なども規定されています。
また、配管は、強度の高い材質を使い、地上に設置する場合は地震や強風で変形しないよう、しっかりと構造物に固定されていなければなりません。
危険物貯蔵所
指定数量以上の危険物を貯蔵する目的で作られた施設です。指定数量とは、危険物の相対的な危険度に応じて定められた数量のことで、例えば、ガソリンの指定数量は200Lで、重油の指定数量は2000Lです。これは、200Lのガソリンが、2000Lの重油と同等の危険度がある、または、ガソリンが重油の10倍の危険性があることを表しています。
法令では、この指定数量の倍数(1倍以上)によって規制が設けられています。
例えば500Lのガソリンと1000Lの重油を同じ貯蔵所で保管すると、倍数は100/200+1500/2000=0.5+0.75=1.25となり、倍数1倍以上なので規制の対象となります。
危険物貯蔵所は、設置場所に応じて、「屋外貯蔵所」か「屋内貯蔵所」に、さらにタンクで貯蔵する場合は「屋外タンク貯蔵所」、「屋内タンク貯蔵所」、「地下タンク貯蔵所」などに分類されます。他に、タンクローリーなどの移動できるものは「移動式タンク貯蔵所」、容量600ℓ以下のタンクは「簡易タンク貯蔵所」に分類されます。
施設の構造、設備、配管も危険物製造所と同様、安全性を担保するための細かい基準が設けられています。
危険物取扱所
危険物取扱所は、危険物の貯蔵だけではなく、危険物の移動を頻繁に行うことを前提とした施設です。扱う危険物の種類や移動目的によって種類が分けられています。一番身近な例でいえば、ガソリンスタンドなどの「給油取扱所」がこれにあたります。
他には、塗料などの危険物を容器入りの状態で販売する「販売取扱所」や、配管やポンプによって危険物を移送するための設備である「移送取扱所」などがあります。
危険物取扱所にも種類ごとに、位置、構造、設備などの基準が設けられています。
まとめ
危険物施設にはさまざまな種類があり、扱う危険物や用途に応じて細かく分類されています。ガソリンスタンドなどの身近な施設から、一般の人が立ち入ることのない製造施設まで、世の中には危険物施設が数多く存在します。危険物は取扱いを間違えると重大事故につながりかねないため、それぞれ細かく規制が設けられています。危険物施設の種類やその違いについては本記事を参考にしてみてください。
